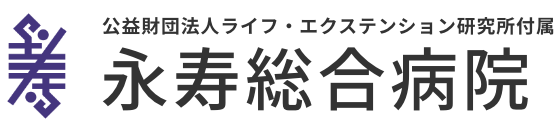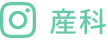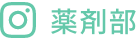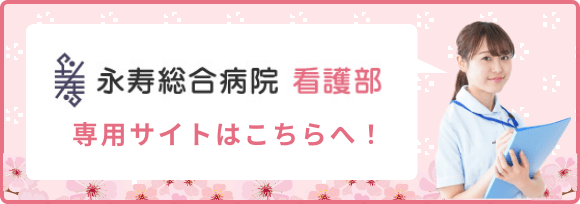開催報告 臨床研究センター × 地域医療連携センター 合同セミナー(2025.07.09)
開催報告 臨床研究センター × 地域医療連携センター 合同セミナー(2025.07.09)
7月9日に当院臨床研究センターと地域医療連携センターの合同セミナーを開催しました。「臨床や研究における生成AIの実践的活用法について」と題して、慶應義塾大学病院臨床研究推進センター 教育研修部門長/広報部門長 特任講師の吉田和真先生をお迎えし、生成AIの基礎から医療分野での具体的な活用法まで、実践的な内容についてご講演いただきました。



生成AIは「最高の相棒」
吉田先生は、生成AIを「24時間、何を聞いても何回聞いても怒らず手伝ってくれる最高の相棒」だと表現しました 。
専門職を対象とした研究で、生成AIの使用により作業時間が平均40%減少し、作業の質が18%向上したというデータも紹介されました
生成AIは、今ある自分の能力や専門性を何倍にも拡張してくれ、一緒にタスクをこなしながら「共創」していくイメージだと説明されました。
共創のためには、以下のような心がけが重要だと述べられました。
- AIを常にタスクに参加させる: AIの能力と限界が理解できるようになるため。
- 人間参加型(ヒューマンインザグループ)にする: AIが生成する「ウソ」をチェックするため。
- AIを人間のように扱う: 上司と部下の関係性のように、指示の仕方でアウトプットが変わるため。
- 今日のAIが今後出てくるAIの中でも最も劣悪である、と認識する: AIの進化のスピードを受け入れるため。
活用時に守るべき4つの注意点
みなさんが「面倒だな」と感じているタスクで、生成AIに任せてもリスクが低いタスクに生成AIをぜひ使ってみてほしい、とご紹介がありました。
例えば、
- 英文メール作成
- チーム内の資料作り
- アイディア出し
- 文献検索
- 論文の要約
などを挙げられました。
そして、生成AIを利用する上で注意すべき点として、以下の4つを挙げられました。
- ファクトチェック: アウトプットされた情報が正確か、必ず確認すること。
- 個人情報の入力制限: 個人情報や機密性の高い情報を入力しないこと。
- 学習されない設定: 入力した情報がAIの学習に利用されないよう設定すること。
- 著作権: 生成されたコンテンツの著作権に注意し、最終的な責任は利用者が負うこと。
これらの注意点を守り、適切に活用することの重要性を述べられました。
医療・研究分野での具体的な活用法
講演では、研究プロセスにおける生成AIの具体的な活用法が紹介されました。ChatGPTやNotebookLM、Manusといった実際のAIツールを用いたデモンストレーションも行われ、論文の要約やスライド作成を効率的に行う様子を見せていただきました。
活用法
- 言語の壁をなくす
英語メール作成や海外の研究論文の翻訳などを生成AIによる精度の高い要約・推敲・翻訳を利用することで、非ネイティブが直面する時間的・労力的負担を大幅に軽減し、効率化できることが示されました。 - AI散歩
散歩中や通勤路などで、いつも携帯していることの多いスマートフォンの音声入力を用いてAIと対話すること。思考や情報のインプットの質を大きく変えてくれ、その効果は想像以上に大きいものになるでしょう、と提案されました。 - 文献検索
会話のように投げかけた質問に対し、関連性の高い論文をAIが自動で抽出してくれます。さらに、抽出された論文の要約や比較、解説の提供も可能なため、専門知識が少ない利用者でも、膨大な文献の中から効率よく目的とする情報を取得することが可能と紹介されました。 - 論文執筆
Nature誌やJAMA誌といった学術誌が、生成AIの利用を認める一方で、ICMJEの規定では、著者としては認めず、使用した場合はその旨を記載するよう求めている現状が解説されました。不適切な利用による論文撤回事例も紹介され、適切な利用と申告の重要性を教えていただきました。
生成AIは「専門性を何倍にも高めてくれるツール」
最後に吉田先生は、「生成AIは決して専門家を置き換えるものではなく、専門性を何倍にも高めてくれるツール」だと述べられました。
若い医師の教育においては、すでに彼らが日常的に利用しているAIを禁止するのではなく、思考を促進する方向への“使い方のルール”やどのように“問いを設計するか”の重要性について語られました。生成AIをうまく活用することで、メンターメンティー双方にとってwin-winの関係性を築ければと述べ、講演を締めくくられました。
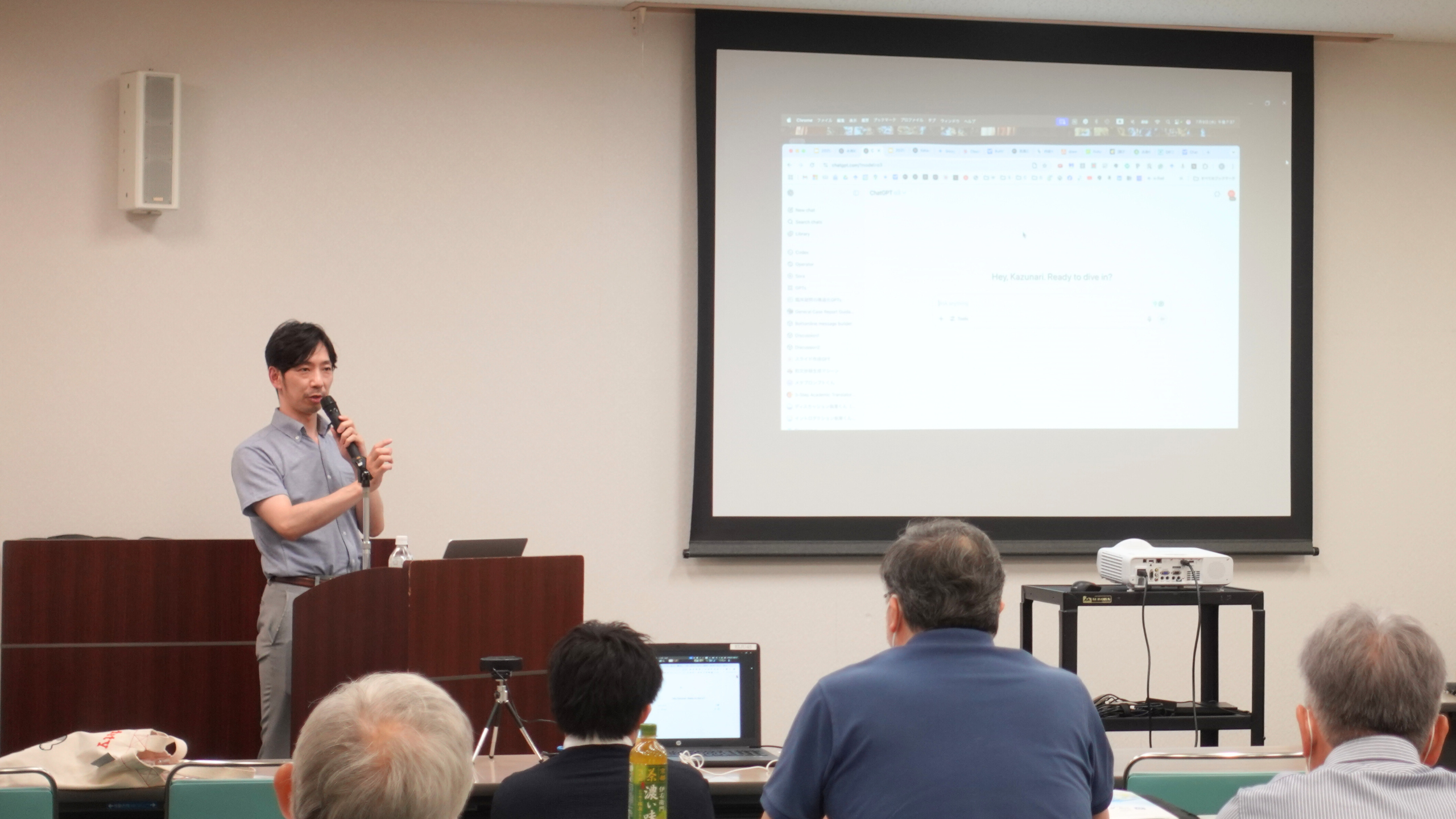

今回の講演会が、先生方の日々の臨床や研究に生成AIを適切に取り入れるきっかけとなり、
病病・病診連携がさらに強化される一助となれば幸いです。
今後も皆様との連携を深めながら、地域医療の質の向上に貢献できるよう努めてまいります。
よくご覧いただいているページ